2021年1月5日の合格発表にて、中小企業診断士試験に合格しました。
3つ年上の妻と、7歳と3歳の娘2人を抱えながら、仕事と育児と勉学に励んだ結果、およそ2年間かけて中小企業診断士資格に独学で合格することができた体験記を綴りたいと思います。 今後、私と同じようにこの資格を目指そうとする子育てパパたちの一助となれば幸いです。(子育てパパに限らず、お読み頂けると幸いです。)
中小企業診断士とは?
中小企業支援法に基づく資格で、簡単に言うと、「中小企業の経営コンサルタントとしての国家資格」です。
学習内容は多岐にわたり、一次試験では「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理(オペレーション・マネジメント)」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・中小企業政策」の7科目からなります。
一次試験に合格すると、2次試験において筆記試験・口述試験があり、どちらも合格し、必要な診断実務経験又は実務補修を経たうえで、中小企業診断士として登録することができます。 1次試験、2次試験の合格率はどちらも20%前後(年度によってブレあり)で、合格までに必要な平均勉強時間は1,000時間以上と言われています。
中小企業診断士資格取得を目指したきっかけ
私の場合、当時の勤務先で海外事業開発に従事しており、海外現地法人設立から運営まで、いわゆる中小企業の経営に関わる業務全般に携わっていました。それがきっかけで「会社経営について体系的に勉強したい」と思いました。本当は海外留学してMBAでも取得できればよかったのですが、幼い娘が2人いる共働き世帯のパパが海外留学など、金銭的にも時間的にも非現実的な話でした。世の中には、MBA取得のための学費や海外生活費用などを支援してくれる企業もあるようですが、残念ながら私の勤務先には、そのような制度はありませんでした。そこでいろいろ調べてみたところ、中小企業診断士資格合格に必要な学習内容が、MBA取得に際して学習する内容と類似していることが分かりました。そこで、2018年10月頃から書店へ足を運んでは、中小企業診断士資格取得に必要なテキストや問題集を購入し、試験突破を見据えながらの勉強を独学で始めることにしました。
独学のメリット
中小企業診断士資格取得のための勉強方法に関して、様々なブログやWebサイトがあり、中には「独学での合格は極めて難しい」旨が書かれているものもあります。確かに、1,000時間以上の勉強時間を要する資格の為、予備校の講義などで学習の進捗度合いを計れるペースメーカーがあった方が、安心という方もいらっしゃるかもしれません。実際に、合格者の多くは、予備校や通信講座等を活用して勉強してこられた方々のようです。
しかし一方でこの資格は、弁護士や公認会計士などといった、合格までに2,500時間以上の学習時間を要するような超難関資格とは違います。合格者の大半は、会社員や自営業者として働く傍らで勉強をして来られた方々です。「働きながら勉強をして合格できるレベルの資格なのだから、独学でやってできないことはないだろう。」私はそう思いました。 更に、独学のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 好きな時間に好きなペースで勉強を進められる。
- 授業を聞くよりも、自らテキストを読んで学習する方が、短時間で入ってくる情報量は圧倒的に多い。
- 予備校に通う為の時間的、金銭的コストがかからない。
これは余談ですが、私は中小企業診断士以外にも、1級ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、TOEIC900点などの資格を有していますが、どれも独学で取得しました。
予備校や通信講座による授業を聞く行為って、すごく受動的です。授業時間中ずっと集中力を持続させるのは、至難の業だと思います。集中していない時間に右から左へ講師の話が流れていくと、実際には頭に入っていないのに、授業に出席しただけで勉強した気になってしまうことが逆にリスクです。
もちろん、勉強方法は人それぞれなので、ご自身に合った勉強方法を選ぶことが肝要なのですが、ほとんどの資格勉強について言えることは、「予備校や通信講座の授業を聞いただけで合格できる訳はなく、自ら能動的にテキストを読んで内容を理解し、問題を解いて知識を定着させる行為なくして、試験合格はできない。」ということです。 1,000時間以上勉強するということはつまり、毎日1.5~2時間の勉強を、2年間継続すれば合格できるということです。1年間で合格したい方は、毎日3~3.5時間の勉強時間を確保すれば合格できるのです。もちろん個人差はありますので、一概には言えませんが、資格取得のための勉強というのはつまり、この必要な勉強時間を確保できるかどうかに尽きると思います。あとは確保した時間内でテキストを読んで理解し、問題演習を繰り返して知識を定着させる。このやり方さえ間違えなければ、だいたいの試験は突破できるのではないでしょうか。
1次試験について
中小企業診断士の1次試験は全てマークシート形式で、各科目100点満点中60点が取れると合格です。
60点に達しない科目があっても、他の科目と併せて全体で6割の点数が取れていれば、合格となります。ただし、1つでも40点未満の科目があると、合格にはなりません。 全科目で6割に達していない場合、又は40点未満が1科目でもある場合には、翌年以降2年間、60点以上取れた科目の受験を免除されたうえで、再度1次試験を受けることができます。(当該科目を免除するかどうかは、自由に選択することができます。)
1次試験対策で使用したテキスト
まず、中小企業診断士試験の概略をつかむために、「最速合格!中小企業診断士 最強入門テキスト」を購入しました。

これは、これから試験勉強を始めるに当たっての、オリエンテーションのような感覚で読むのが良いと思います。私の場合、新品を買うお金も勿体ないと思ったので、3年度程前の古いバージョンを、ブックオフで購入しました。試験の概略や、勉強をするに当たっての心構えなどを理解する為のものとして、2週間程度で読み流すぐらいがちょうど良いのではないかと思います。これを読んだおかげで、試験に関する大まかな全体像を把握できたように思います。
次に購入したテキストは、TAC出版のスピードテキスト、スピード問題集です。

これらを各科目1冊ずつ揃えて行きました。毎年9月から12月にかけて、翌年度試験に対応した更新版が順次発売されていくので、発売された科目から順に買っていき、勉強を進めていきました。
1次試験勉強の進め方
まずは、スピードテキストをそれぞれ流し読みして、どのようなことが書かれているのかの大枠をつかみます。
その後、スピード問題集を使って問題を解きながら、分からない箇所はスピードテキストに戻りながら、暗記を進めていきます。分からない箇所がなくなるまで、スピード問題集を各科目3回ほど繰り返します。
一次試験の1~2か月ほど前になると、それまでスピードテキスト、スピード問題集で学習した内容の定着度合いを測るために、過去問に取り組みます。過去問はそれぞれの科目でとりあえず2年分程度解きました。
過去問を自己採点していると、自分の得意科目、苦手科目が分かってきます。
私の場合、得意科目は、企業経営理論、運営管理、財務・会計でした。
逆に苦手科目は経営情報システム、経済学、中小企業経営・中小企業政策でした。
経営法務については、苦手意識はなかったものの、実際に出題される内容が細かい点まで問われるため、過去問演習では合格ライン1歩手前をさまよっていました。
企業経営理論や運営管理は、普段からの実務に結びつく内容が多いため、理解しやすく、勉強していて楽しかったです。過去問2年分を解いていても、常に合格点である60点以上を取れていました。
財務・会計は、当時の勤務先でもよく使う知識が多く、一番の得意科目でした。ただし、普段から実務で使わない方にとっては、越えなければならない高い壁となることもあるようです。簿記2級程度の知識を持っておくと、勉強しやすいという話をよく聞きますし、私自身もそのように思います。
逆に、比較的得点しやすいと言われる科目である、経営情報システムは、普段から私が苦手としているITに関する分野であり、私にとってはチンプンカンプンでした。
中小企業経営・中小企業政策も一般的には得点しやすいと言われている科目のようですが、私にとってはあまりなじみがなく、暗記しなければならない項目も多く、特に中小企業白書からの出題については、毎年問われる内容が違い、過去問対策も通用しないことから、私にとっては非常に勉強しにくかったのを覚えています。
経済学についても、初めて勉強する分野であったため、内容を理解するのに時間がかかりました。
以上から、1次試験3週間前からは、とにかく苦手意識の強い経営情報システム、経済学に重点を置いて問題演習をこなしていきました。中小企業経営・中小企業政策も苦手ではありましたが、試験対策について書かれたあらゆるWebサイトを閲覧しても、もはや「中小企業白書を読んで暗記するだけ」といったような対策方法しか書かれておらず、試験までの残り日数もわずかだった私は、「なるようになるだろう」と半ば投げやりでした。
1次試験結果
2019年7月に受験した1次試験の結果は以下の通りでした。

各科目の自己採点結果は以下の通りです。
経済学・経済政策 60点
財務・会計 76点
企業経営理論 44点
運営管理 62点
経営法務 56点
経営情報システム 72点
中小企業経営・中小企業政策 42点
合計 412点
7科目全体で420点取れれば、6割に達するのですが、残念ながら8点足りず、不合格でした。
科目別に見ると、もともと得意科目だった財務・会計は得点源となりました。また直前に分からないながらも詰め込んだ経営情報システムも、意外と高得点を取ることができました。
一方で最後まで投げやりになってしまった中小企業経営・中小企業政策は、案の定、燦燦たる結果でした。経営法務も、学習が足りず、あと1問のところで不合格となってしまいました。
驚いたのは、過去問で常に合格点を取れていた企業経営理論の点数が全く足りなかったことです。「そこまで勉強しなくても問題ないだろう」と高を括って、試験直前での詰め込みをおろそかにした結果、知識が抜け落ちていったのだと思われます。
このように、中小企業診断士1次試験でストレート合格を狙う場合、7科目全てを満遍なく勉強しなければならないという難しさがあります。私も、「あわよくば一発合格!」と意気込んで受けた初の1次試験でしたが、惨敗でした。一方で、この試験の受けやすいところは、1度合格した科目は、翌年度以降2年間、再受験の際に免除してもらえるということです。
もちろん、翌年以降も科目免除せずに再受験をし、受験した全科目の合計得点で全体の6割を目指すという戦略もあります。しかし私の場合、一度合格した科目の為に、翌年度も再度試験対策をする気力までは湧きませんでした。従って、科目不合格となった3科目(企業経営理論、経営法務、中小企業経営・中小企業政策)だけを再度受験する戦略を選びました。
結果、翌年度2020年7月に再受験した1次試験の自己採点結果は以下の通りです。
企業経営理論 72点
経営法務 76点
中小企業経営・中小企業政策 64点
相変わらず中小企業経営・中小企業政策は苦手科目のままでしたが、各科目とも60点超えを果たし、危なげなく1次試験を突破することができました。

1次試験勉強の反省
1次試験の勉強を進めるにあたり大変なのは、学習しなければならない科目数の多さです。
1発合格を目指す場合には、7科目全体で6割を取れるように学習をしなければなりませんが、その為に必要な努力は生半可ではありません。7科目もあると、他の科目を学習しているうち、以前にやっていた科目の内容を忘れていってしまうのです。
私の場合、妻と娘たちがまだ寝ている朝の4時に起きては、一人リビングでテキストや問題集を開いて学習をしていました。また通勤電車の中も、学習時間を確保できる貴重な空間です。電車の中で必ずテキストや問題集を開く習慣をつけていました。このようにして毎日必ず2~3時間の学習時間を確保するようにしては、コツコツと勉強を進め、試験前3週間ほどは、会社の昼休みも活用して問題集を開いていました。
それでも結局ストレート合格は叶わず、翌年に科目免除のうえ再受験をすることで、ようやく1次試験を突破することができました。
2~3年かけて中長期的な学習計画を立てられる方は、年度毎に学習する科目を絞って、確実に科目合格を目指すというのも、1つの戦略だと思います。
勉強する際のコツ
私の場合、勉強している間は極力立ちながら、又は歩きながらの姿勢で学習するようにしていました。人は座っていると、体が休むように作られているそうです。立ちながら、または歩きながら学習することで、脳が活性化され、集中力が持続します。自宅で歩きながらテキストを読んでいるところを妻に見られたときは、「二宮金次郎か!」と突っ込まれましたが。

また、1次試験学習では、暗記しなければならない事項も多くあります。そのような時は、暗記すべきワードを声に出すことで、耳からもその情報を取り込むことができるようになり、五感をフルに活用して知識を定着させていくことができます。ただし、家族の迷惑にならないよう、声の大きさには要注意です。私の場合、毎朝4時に起きて、リビングを歩き回りながらテキストを音読していると、妻が起きてきて、「こんな時間に何やってるの?誰かいるのかと思った。不気味だからやめて。」と注意されてしまいました。
2次試験について
1次試験を合格した方のみ、毎年10月に実施される2次試験の筆記試験を受験することができます。
ここでは、Ⅰ~Ⅳの4つの事例とそれに対する設問が5~6問ほど与えられます。試験時間は各事例ともに80分で、各設問に対しては最大120字程度の論述回答が求められます。

各事例で必要となる関連知識は以下の通りです。
事例Ⅰ・・・組織・人事
事例Ⅱ・・・マーケティング・流通
事例Ⅲ・・・生産・技術
事例Ⅳ・・・財務・会計
2次筆記試験を突破する為には、全事例合計で60%以上得点できており、かつ各事例ともに40%未満の得点がないことが必要となります。
2次試験対策について
この二次試験、出題者である中小企業診断協会から公表されている模範解答や採点基準などはありません。試験後に、各予備校がWeb上で模範解答を発表しますが、その内容も予備校ごとで違います。つまり受験生にとっては、独自に過去問演習をしたところで、自分の作成した答案が合格基準に達しているのかどうかが分からないのです。
2次試験対策で使用したテキスト
このような状況下で、独学で二次試験対策をしたい方にお勧めなのは、ふぞろいな合格答案シリーズです。

これは、過去の2次筆記試験受験者の再現答案及び、その受験生の獲得点数を集計して、独自に過去問の模範解答や採点基準を出しているものです。私はこのテキストを信じて学習を進めた結果、2次試験は一発で合格することができました。
2次試験対策期間
大半の受験生は、1次試験受験後すぐに自己採点をして、1次試験を突破しているだろうことが分かれば、その後すぐに2次試験対策に取り組みます。つまり、7月上旬の1次試験後から10月下旬の2次試験まで、およそ3か月間の2次試験対策期間があるのです。
しかし、私の場合は少し事情が違っていました。実は私は当初、2020年7月に受験した1次試験を合格後、2020年10月の2次筆記試験の受験は見送り、翌年2021年10月の2次筆記試験を受験する計画を立てていました。実務で携わっていた不動産関連資格の勉強を同時進行で進めており、その資格の試験日が、中小企業診断士2次筆記試験と重なっていたことが理由です。(1次試験合格後、同年に2次試験を受験しない場合は、その翌年から2年間、2次試験の受験資格を保持できます。)
しかしながら、その不動産関連資格の試験日が、コロナウイルスの影響で2か月延期となりました。その延期通知を受け取ったのが、中小企業診断士2次試験受験申込締切日であった9月18日の前日でした。その通知を見た私は、翌日の締切日当日に2次試験申込をし、その足で書店に行って、2次試験対策用テキストを購入し、2次試験対策を開始しました。 私の場合、2次試験対策を始めた時点で、2次試験日までの学習可能期間が残り1か月間しかなかったのです。
2次試験対策に必要な学習時間
一般的に、2次筆記試験対策は、過去問5年分について、時間内で答案を作成する演習を繰り返し3回行うことが必要と言われています。(もちろん個人差はあります。)
1年分の2次筆記試験問題に事例Ⅰ~Ⅳまでがあり、各事例を解く際の制限時間は80分です。問題を解いた後に、テキストの解説を読むのに各事例で平均80分必要だと想定すると、1年分の過去問学習に必要な時間は(80分+80分)×4事例=640分です。さらにこれを5年分、3回繰り返す必要があるので、2次筆記試験対策に必要な学習時間を見積もると、640分×5年分×3回=160時間ということになります。
私の場合、この学習時間を残り1か月間でこなす必要がありました。そうすると1日あたりに必要な平均学習時間は5~6時間です。昼間はフルタイムで会社勤務していて、自宅に戻ると子供たちをお風呂に入れたり、寝かしつけたり、皿洗いをしたりといった家事育児も欠かすことのできない私にとって、1日に確保できる平均学習時間はせいぜい3時間ほどでした。かくして、いかに効率よく2次筆記試験学習を進めるかが、私にとっての課題でした。
2次試験対策で工夫したこと
まず、問題演習をするにあたり、本番同様、方眼用紙に手で答案文を書き込んでいく方法が理想的ではありますが、時間のない私は、パソコンでワードファイルを開き、そこに答案文を打ち込んでいくことにしました。手で書くのにかかる時間の短縮を図ったのです。頭に浮かんだ解答のアウトプット方法が、手で書くか、ワードで打ち込むかの違いだけなので、学習効果としてはあまり変わらないだろうと考えました。 また、実際にこの答案作成作業をしたのは、過去問5年分の演習を2回繰り返すまでで、3回目の答案作成は行わず、事例問題を読んで、合格答案に必要なキーワードを頭の中で組み立てていくという作業に終始しました。3回目の過去問学習ともなると、試験日まで残り数日しかない状況に追い込まれており、もはや答案作成の時間を捻出することもできず、とにかく与件文と設問を読んで、必要な答案を頭の中に思い浮かべるトレーニングをするのが関の山でした。
2次筆記試験の結果
こうして、十分な学習時間を確保できないまま臨んだ2次筆記試験でしたので、試験当日も「ダメでもともと。来年また受け直せばいい」というリラックスした気持ちで問題を解いていきました。試験を終えた後も、あまり自分の中で手応えは感じられませんでしたが、(そもそも正式な模範解答や採点基準もないので、筆記試験通過者発表の日まで、合否を確信することなどできません。)何とか筆記試験を通過することができました。

2次筆記試験合格に必要な知識とコツ
2次試験を受けて感じたことは、財務・会計の知識を要する事例Ⅳ以外は、高校生時代に国語の現代文の問題を解いていた感覚に非常によく似ているということです。1次試験を突破した方なら、2次試験の為に新たな知識を改めて身に着ける必要はありません。
各事例では、与件文で架空の中小企業が登場し、それが抱えている問題や現在置かれている状況などを把握し、それに対する中小企業診断士としての助言を制限時間内で制限字数内にまとめていきます。ふぞろいな合格答案で学習をすれば分かりますが、2次筆記試験を突破する為には、与件文に書かれている内容やそこから連想されるキーワードを確実にひろっていき、制限字数内にまとめる訓練が必要なのです。
過去5年分の過去問を繰り返し演習していると、合格答案作成に必要なキーワードもパターン化されていることに気づいてくると思います。そうなれば、あとは試験本番で落ち着いていつも通りに答案をまとめていく作業をすれば、きっと2次筆記試験は突破できることと思います。
財務・会計の知識が必要な事例Ⅳについては、財務諸表の読み取り能力や、CVP分析やDCFを使いこなせる知識が必要なので、この分野が苦手な方にとっては、少し厄介かもしれません。しかしながら、これらも1次試験で学習した内容から大きく逸脱することはありません。過去問を解きながら、つまずいた箇所は1次試験のテキストに戻りながら、学習を進めていくのがよいと思います。
2次口述試験について
2次筆記試験を突破すると、いよいよ2次口述試験を受験する資格が与えられます。口述試験は面接形式で行われます。私が受けた時は、面接官2名が、2次筆記試験の事例から2つを選んで、内容を口頭で質問され、それに対して口頭で回答するという形式です。私が受けた時は、面接官2人で1つずつ事例を取り上げ、それに対する質問を2個ずつ、合計4つの質問に答える形式でした。1つの質問に対して、2分間の回答時間が与えられるので、「慌てず、落ち着いて答えてください。」と最初に面接官から説明がありました。
ここまでくれば、ほぼ中小企業診断士試験に合格したと言っても過言ではありません。過去の試験結果を見ても、この口述試験で不合格となる確率は1%未満です。受付時間までに会場に到着し、口述試験中に黙り込んでしまうようなことさえなければ、この試験は突破できると言われています。
2次口述試験対策
とはいえ、1%未満の不合格者となることを避けるためには、ある程度の準備は必要です。
私の場合は、口述試験1週間前から、2次筆記試験の事例Ⅰ~Ⅳを読み返して頭の中に入れ、各予備校がWeb上で公表している想定問答集を見て、想定される質問に自分の言葉で答えられるよう、イメージトレーニングを繰り返しました。 口述試験対策として費やした時間は、合計で10時間程度だったと思います。
最後に
いつもは家族で出かけた際のブログばかり書いている私ですが、家族と過ごす時間の裏で、実は中小企業診断士試験に合格する為にコツコツと勉強を積み重ねておりました。
中小企業診断士試験に合格する為には、越えなければならない関門が多く、決して簡単な試験ではありません。しかしながら、計画的にコツコツ学習を進めていけば、幼い子供を抱える共働き世帯のパパでも、家族と過ごす時間の傍ら、独学で試験に合格することは可能です。
これから中小企業診断士試験合格を目指す方々にとって、これまでに記載した内容が何かのヒントとなれば幸いです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
おしまい。
人気ブログランキングに参加しました。
よかったら、以下のバナーをクリックして投票してください♪
※サイトが表示されたら投票完了です。
※1日1クリックまで投票できます。

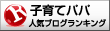

コメントを残す